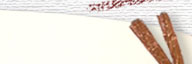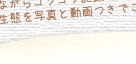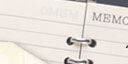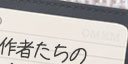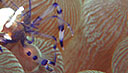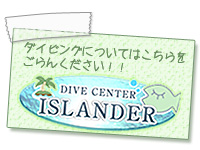お店の水槽にいる“ハリセンボン”は「ポッチ」って言います
ヾ(〃^∇^)ノ
和名 針千本
学名 Diodon holocanthus
英名 Ballon Porcupinefish
(Porcupine=ヤマアラシ)
フグ目フグ亜目
ハリセンボン科ハリセンボン属

ハリセンボンは『フグ目』の『フグ亜目』に属します
『フグ亜目』には、フグ科、ハリセンボン科、マンボウ科があります
また、『フグ目』には、カワハギ科、モンガラカワハギ科、ハコフグ科などが
あります
*************************
『名前の由来』
うろこが変化した、長く強いとげが体表に数多くあるのが和名の由来
Ballon= 風船/Porcupinefish=ヤマアラシという英名もここに由来する
危険を感じると、体をボールのように膨らませて針のような頑丈な棘をたてる
ですが、和名のように針が千本あるわけではなく、だいたい350本前後
だそうです
『生息地』
日本では津軽海峡以南の日本海沿岸、相模湾以南の太平洋岸、琉球列島
全世界の熱帯から温帯域に広く分布し、6属20種類ほど
比較的浅い海(水深40m以浅)の、岩礁域や砂地などに生息しています
岸から離れて群れを作ることもあります
『代表的なハリセンボン科の仲間たち』
全長は15cmほどのものから70cmを超えるものまで
日本近海で見られるのは、下記の4種です
●ハリセンボン(全長40cmほど)
体色は、褐色系で、まだら模様には変異があり個体差があります
体に小さな黒い斑点がたくさんあるが、鰭(ひれ)には斑点がない
ヒレは無色で、黒目はグリーンだったりブルーだったりします
●イシガキフグ(全長60cmほど)
表情はネズミフグに似ていますが、ハリが短く点が少ない
体を膨らませてもハリセンボンほどではありません
●ヒトヅラハリセンボン(全長50cmほど)
茶色のぶちが白く縁取りされているのが特徴で目のぶちも下に伸びている
ハリセンボンよりも大型で、沖縄で食用にされているのはこの種がほとんど
●ネズミフグ(最大で80cm以上に達する大型種)
顔が四角っぽく体にも鰭にも小さな黒い斑点が多く大型はかなり細身になる
ハリは長めで、黒目が大きい
フグはみな可愛いけど、やっぱりハリセンボンが一番愛嬌があって好きです
ここからは、そんなハリセンボンについて調べてみました

『ハリセンボンの特徴』
だいたい30cmほどになる
腹びれがなく、顎の歯が癒合している
皮膚が厚く、敵に襲われると水や空気を吸い込んで体を大きく膨らませる
肉食性でフグ科と共通した特徴を多く持っているが、フグ科の歯は上下2つずつ、合計4つになっているのに対し、ハリセンボン科の歯は上下1つずつ、合計2つ
ウロコが変形した可動性の大きな棘(針)が多数ある
また、フグによく似るが毒はない
やっぱりないんだぁ〜
"φ(゜□゜*(゜□゜*)φ"
ハリセンボンのその姿を思い浮かべた時、ほとんどの方は膨らんだ姿を
思い浮かべるのではないでしょうか?
私も、ハリセンボンはいつでも丸く膨らんでいるものだと思っていました
初めて海で自然の姿をみたとき「地味いぃ〜」って思ってしまいました
これ「ハリセンボン??」って違和感があったのを覚えています
ダイバーならご存知の通り、普段は棘(針)を後ろの方に向けて体に
ぴったりとたたんでいます
『どんな時にまんまるに膨らむ?』
ズバリ、威嚇のために膨らみます
敵の攻撃から逃れるために体を丸い風船のように膨らませ、
棘(針)を立ち上げます
この棘(針)は普段は寝ていますが、体を膨らませた際には直立し、
敵から身を守ると同時に自分の体を大きく見せています
興奮すると約1秒くらいの速さで膨らむことが出来ます
『では、どうやって膨らむ?』
胃に特殊な弁(可変式の一方向弁)があり、そこに海水や空気を取り込み、
体を膨らませ、棘(針)を立てる
通常の体の約2倍に膨らむことが出来ます
膨らむのは約1秒くらいの速さで出来ますが、中の水を吐き出して
元の大きさになるのには2〜3秒かかります
『天下無敵!!』
成長したハリセンボンには、天敵となる生物は殆んど居ないようです
最強!! カッコイー ┌|゜□゜;|┐
時々、マグロの胃からハリセンボンが出てきたり、
サメがハリセンボンを誤食して餓死する事があるようです
天敵は殆どいないハリセンボンですが、遊泳力が弱い為か、
本来は熱帯性のハリセンボンが 暖流に乗って北上し、
水温が低下する冬季に海岸に大量に漂着する事があります
これらの漂着個体は、低い水温に耐え切れず死んでしまいます。。。
『あまりにも有名なフグ提灯』
よく売っていますね・・・
よく飾られていますね・・・
小さい頃から、よく目にしましたよね(!?)
ハリセンボンの本来の姿を見た時に違和感があったのは、
このせいだと私、思うのです
冬になると、日本海に入りこんだハリセンボンが寒さに弱って、
海岸にたくさん打ち上げられることがしばしばあります
私、テレビで見たことがあります
波打ち際で力なく漂いながら泳いでいるハリセンボン
死んでしまって浜にうち上げられているハリセンボン
。・゜゜・(>_<;)・゜゜・。
凍えるように小さくなって。。。
『ここまでよくがんばって泳いできたね』 どばーっ (┬┬_┬┬)
どういう経緯でそうなったか分かりませんが、
“フグ提灯”には魔除の意味があるそうです
もちろん漂着したハリセンボンには全く罪はありませんっ!
ですが、その地域の漁業には多大な被害が出ているそうです
きっと、剥製にするしかなかったのかな。。。
(生きたままのハリセンボンを捕獲して、提灯にする。。。
それが売れるからという理由で行われていたらツライです
こういう話は、キリがないですし、本題とそれますので省きます)
『そのお味は美味』
無毒で美味しいそうです
鍋料理、味噌汁、唐揚げなどで食し、沖縄ではハリセンボンのことを
“アバサー”と呼び“アバサー汁”は有名な沖縄料理の一つだそうです
ただ、硬い棘と皮をやっと取り除いて、残るのはほんの少しの身だけで、
調理するのがとても大変なようです
ちなみに、毒は持っていないので、ふぐ調理師免許がなくても調理可能
だそうです
『人を認識する ┌|゜□゜;|┐』
人によく馴れ、視力もいいようです
そうなのです!!!人を識別します!
うちのポッチは、明香のことが一番好きです
明香がそばを通ると、めざとく見つけて大急ぎで水面まで上がってきます
口から水をゴボゴボ吹き出し、えさをねだっています
かわいーO(≧▽≦)O
怒ったりした場合、ギーギーという音を出して鳴くこともあるそうです
機嫌がいいとニコニコ寄ってきて、機嫌が悪いと露骨にプイっと向こうを向く
ツノ(頭の上の針)を立てて、怖い顔して暴れて自己主張したり、
訳の分からない行動に出たり、表情豊かでとても面白いです
尚、ハリセンボンは、産卵間近の雌でない限り雄雌の識別は困難だそうです
寿命については定かではないようですが、年をとると、歯の力が衰え、
硬いものを割ることが出来なくなります
顔も目の周りに小じわが増えてきたり、色ツヤも悪くなってきます
人間と同じだ!φ(≧。≦)
『においも分かる ┌|゜□゜;|┐』
鼻のところに突起があるのですが、このような突起があることで、
鼻の穴に水が入りやすくなり、においを感じやすくなっているようです
(はっきりは分かってないようですが・・・)
『はりせんぼんのます』
「“はりせんぼん” の〜ますっ!」
この“はりせんぼん”は、針千本なのか、ハリセンボンなのか。。。
この歌、コワイんですね〜
(ノ゜ρ゜)ノ ォォォ・・ォ・・ォ・・・・
まぁ、この“はりせんぼん”は針千本らしいですね
『おまけ』
[所さんの目がテン!]という番組で、ハリセンボンの針を数えてみるという
企画があったそうです
針の数は、352本でした
ある人が、673尾のハリセンボンの針の数を数えてみたところ、その平均は353本だったそうです
アイランダーの水槽に“ポッチ”が来てからというもの、ハリセンボンが大好きになり、海でも見れると大興奮しちゃいます!
本当にカワイイんですよぉ〜
見ていてあきない魚です!魚っていうより犬に近い。。。
なので、“ポッチ”ってつけました
(*´σー`)
みなさんも会いに来てくださいね〜♪
それでは、(*'-')ノ*:・・:*またねー*:・・:*
ぽっちは勝手に?膨らみます。
背伸びみたいなものですかね。
下は膨らんでいるところを写真に収めて縮んで行く様子を撮ったものです。

↓

↓

↓

maekumi